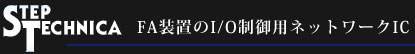FAQ:HLS(Hi-speed Link System)
HLS(Hi-speed Link System)製品に対してお客様からお寄せいただいた質問を下記にまとめました。
製品や技術に関して直接お問合せいただく前に、下記のFAQをご覧ください。
よくある質問一覧
HLSファミリFAQ
CUnetファミリFAQ
![]() CUnetファミリに関するFAQは、こちらから。
CUnetファミリに関するFAQは、こちらから。
質問と回答
| HLS(Hi-speed Link System)とは、どういうシステムですか︖ | 1個のマスタICと最大63個のスレーブICによって、超高速にリモートI/Oを制御する省配線を⽬的としたシリアル通信システムです。 |
| イーサネットなどとは、どの様な違いがあるのでしょうか? | イーサネットをはじめとするLANなどにおいて使われるネットワークは、⽐較的⼤きなデータを転送しています。 更に、イーサネットはCSMA/CDという⽅式を採⽤しており、送信したデータがいつ相⼿に届くかは保証されていません。 HLSは、転送するデータをI/O情報に特化することにより、プロトコルの単純化と⾼速化を図り、ポーリング⽅式の通信によって、制御に利⽤可能なリアルタイム性も確保しています。 |
| 「1msの応答速度」とは、どのような意味ですか︖ | 「1ms」とは、1/1000秒のことです。 ⾳は空気中を1秒間に約300m進むと⾔われていますから、⾳でさえ30cmほどしか進んでいない間に、⼊⼒に対する反応を返すことができる時間という意味です。 HLSでのI/O点数は2016(⼊⼒は1008点/出⼒は1008点)であり、この全てのI/O点数を1msで扱うことができます。 |
| シリアル通信の場合、通信の信頼性が気になります。 | HLSは、RZ符号検定、パケットフォーマット検定、CRC12検定、といったデータの信頼性を保つための検定を何重にも実施しています。また、CUnetではCRC16を採⽤しています。 エラーが検知されたパケットは破棄されるため、ユーザが誤ったデータを取得することはありません。 |
| HLSの割り当てるサテライトアドレスは、連続した番号でなければなりませんか︖ | システム上はその必要はありません。また、物理的に小さい値のアドレスから順番通りに並んでいる必要もありません。 ただし、HLSはサテライトアドレスのSA.1から、指定した運⽤数の中において最⼤アドレスを持つサテライトまでを対象としてポーリングを実⾏しますので、サテライトアドレスはなるべく詰めて(番号を続けて)番号を割り当て、運用数を少なくした方が⾼速な応答速度を実現することができます。 |
| HLS に採⽤されているエラー検定の能⼒を教えてください。 | HLSが採⽤しているCRC12検定の検定能⼒は、下記の通りです。 m=CRCの⻑さ b=誤りのビットの数 b≦mの時・・・・・100% b=m+1の時・・・(1-(1/(2m-1)))×100% b>m+1の時・・・(1-(1/(2m)))×100% 12ビット以下の誤りに対して・・・100% 13ビットの誤りに対して・・・・・99.951% 14ビット以上の誤りに対して・・・99.975% チェックやフォーマットチェックなども同時に実効しているので、限りなく100%に近い検定能⼒を持っています。 CUnetも同様に考えられます。 |
| 伝送距離の保証値は何 m ですか︖ | HLSの伝送距離の⽬安は、12Mbpsの場合100m、6Mbpsの場合200m、3Mbpsの場合300mです。 これは、32ステーション(装置)のブランチ状況における⼀般的な利⽤を想定したものです。 しかし弊社における実験結果よりも余裕を⾒た値であり、これ以下の伝送距離であれば、評価をしなくとも実⽤されているケースがほとんどです。 しかし、伝送距離は、ケーブルの種類や引回し状況、ブランチ数、また、その他の周辺環境によって⼤きく変わります。 弊社は、使⽤環境を⼀切規定していませんので、伝送距離についても弊社が保証するものではありません。 |
| HLS の伝送ケーブルを 1km 程度に延ばす⽅法はありますか︖ | MKY02を使⽤することにより可能です。 HLSの電送距離の⽬安は、12Mbpsの場合100m、6Mbpsの場合200m、3Mbpsの場合300mですので、3Mbpsにて動作させた場合、途中(300mごと)にMKY02を3個挿⼊することにより1.2kmのネットワークを構築することが可能です。ただし、弊社は、使⽤環境について⼀切規定していませんので、弊社が保証するものではありません。 |
| 誤って同じアドレスのサテライトを複数存在させた場合、どのようにして発⾒することができますか︖ | センタのコマンドエリアを確認すると、サテライトアドレスが誤って指定された端末は、永続的な通信エラー(存在しないため)になっています。本来、あるべきサテライトアドレスが永続的な通信エラーになっているのであれば、同じアドレスのサテライトが存在すると判断できます。 |
| SCR(Syestem Control Register)へ運⽤台数を書き込みましたが、HLS メモリの内容は変わりません(端末からの出⼒もありません)。オシロスコープによって通信ラインを確認したところ、全く通信は稼動していないようです。どのような原因でしょうか︖ | 原因はいくつかに分けられますが、以下の点を⾒直してください。 ・センタICへのクロック、リセット及びリードライトタイミング。SCRへ書込みしたデータは、正しく読み込み可能でしょうか。 ・BPS設定が(誤って)EXC設定になっているのにもかかわらず、EXC端子へクロックが供給されていない。 |
| 差動ドライバ / レシーバの選択⽅法を教えてください。 | ドライバは、「RS-422」または「RS-485」に対応しておりかつ利⽤する転送レートをサポートしているのであれば、ほとんどの部品を使⽤可能と思われます。 ⼀⽅、レシーバは、レシーブ感度が伝送レートに対し⼗分な部品を選択することが必要です。 カタログスペック上においては、レシーブ感度として200mVp-pとなっていても、⾼速レート時には3Vp-p程度が⼊⼒されていなければ、正常に信号を再⽣しない場合もあるようです。 ■レシーバは以下のような⽅法等によって事前に評価することをお薦めします。 12MbpsのRZ信号は、ビット変化が最も速い部分は6MHzクロックと等価となります。 したがって、6MHzのクロック相当の信号(サインカーブでも良い。デューティが50%の信号)を、ファンクションジェネレータ等の発振器(⽔晶発振器でも良い)によって⽣成し、レシーバへ⼊⼒します。 後は、そのクロックの振幅を、ボリュームや抵抗分割によって絞って⾏きながら、どの振幅レベルまでレシーバの出⼒側にデューティ50%の正常な再⽣が得られるかを観測します。 正常に再⽣可能な最⼩の信号振幅が、そのレシーバの⼊⼒感度です。 (⽬安としては、300mVp-p以下でも、正常に受信できるレシーバが良好です) (当社のボード製品には、SN65C1168<TI社>、ADM1485<アナログ・デバイセズ社>などを利⽤しています) |
| MKY36はどんな CPU と接続できますか︖ | 8/16ビットのデータバスを持ち、WAIT⼊⼒が可能なCPUをご利⽤ください。 あるいは、ウエイトステートの挿⼊によってアクセス時間を⼗分に設定できるCPUでなければなりません。 エンディアンはビッグとリトルの両⽅に対応しています。 【注意】MKY33には、数種類の接続⽅法がありますが、CPUによっては接続⽅法が制限される場合があります。 |
| アナログデータを⼊出⼒できますか︖ | MKY34およびMKY37が提供できるI/Oは、デジタル16イン/16アウトのみです。その先にD/A変換器やA/D変換器などを付けてご使⽤いただいてる事例もございます。ただし、アナログデータの入出力のタイミングとHLSのデータ更新タイミングについて考慮する必要があります。アナログデータを取り扱う場合、CUnetでの構成をご提案いたします。 |
| MKY34とMKY35とMKY37を混在させたシステムを構築できますか︖ | できます。物理的な位置関係やアドレス設定などにも⼀切制約はありません。 MKY34、MKY35、MKY37あわせて1システムの最⼤サテライト数(63ノード)以下であれば⾃由に配置することができます。 |
| HLSとCUnetを一つのネットワーク内に混在させて構成することは可能でしょうか? | HLSとCUnetを1つのネットワーク内に混在させることはできません。 |
| 通信ケーブルは、どのようなものを選べばよいでしょうか? | イーサネットLAN用のカテゴリ“5”性能以上の通信ケーブルを推奨します。シールドが施され伝送品質が高く、かつ加工性に富んだ推奨ケーブル(ZHシリーズの通信ケーブル)も用意されています(販売代理店へお問い合わせください)。 |
| 推奨パルストランスと水晶発振器及び推奨ケーブルの詳細資料が欲しいのですが。 | 弊社が推奨している各種部材につきましては、弊社製品とあわせてご購⼊いただくことが可能です。 各種部材の資料につきましては、弊社代理店にお問い合わせください。 また、弊社ホームページの推奨周辺部品のページからも資料をダウンロードいただくことができます。 販売元 パイオニクス(株) 042-566-1231 https://www.steptechnica.com/jp/pe/index.html |
| アーク溶接の作業をしている⼯場においては、ノイズによる影響が⼼配です。このような現場に使⽤できるでしょうか︖ | 推奨伝送路を使用した場合における実績はあります。しかし、あるフィールドにおいて使用可能かどうかの評価は、実際に現場においてテストするのが一番です。HLSには、通信エラーの発生をパルスによって知らせる機能がありますので、実際の現場におけるエラー発生率を事前に調査することによりHLSを使用できるかどうかの目安にすることができます。アプリケーションにもよりますが、連続3回のエラー発生を知らせる「CHK2パルス」が発生しない環境が使用可能の一つの目安となります。 |
| HLSを評価したいのですが、どのような⽅法がありますか︖ | 動作の概要を簡単に体験するために、PCIバスやPCIExpressバスに対応したセンタボードもあります。また、USB接続に対応したセンタボードもあります。 このセンタボードは、Windows⽤のドライバやライブラリが添付されていますので、⼿持ちの開発環境によって⽐較的簡単にプログラムを使った検証が可能です。 端末側は、HLSB-37T2I/OというMKY37の評価ボードをご利⽤になれます。 ただし、ノイズテストなど、破壊の恐れがあるテストに対しては、保護回路が存在しないHLSB-37T2I/Oは利⽤できませんのでご注意ください。 |
| HLSを利⽤して現⾏システムの効率化を図りたいので、市販されているユニットやモジュール製品を紹介してもらいたい。 | HLSを利⽤したリモートI/Oモジュールなどの様々な製品が各社から販売されています。 現行システムの構成をお聞かせいただき、ご提案させていただきます。 |
| MKY37とは、どのようなLSIですか︖ | HLSのサテライト素⼦として、I/O(16/16)だけの機能を内蔵した汎⽤的なモデルです。 MKY34同様、センター素⼦からコントロールすることで、CPUを必要とせずに端末としての⼊出⼒動作を⾏います。 また、MKY34よりコンパクトなパッケージであり、消費電力も少ないです。 |
| MKY37のカスケード接続⽅法について教えてください。 | MKY37ユーザーズマニュアルの付録2に掲載しているカスケード接続の参考回路図をご覧ください。 |
| MKY34とは、どのようなLSIですか︖ | HLSのサテライト素⼦として、I/O(16/16)、カウンター、シリアル⼊⼒レジスタを内蔵した汎⽤的なモデルです。 センター素⼦からコントロールすることで、CPUを必要とせずに端末としての⼊出⼒動作を⾏います。 |
| MKY34 の CLR 端⼦へ Hi が印加されている間、Di データは必ず FFFF H になっていますが、問題はありませんか︖ | MKY34のCLR端⼦にHiが印加されている間にセンタICからDiリードのコマンドを送った場合は、返されるDiデータが必ずFFFFHになります。MKY34ユーザーズマニュアル 「3.5_16本の入力端子(Di)」の「注意事項」をご参照してください。 |
| 全体MKY34の評価中ですが、まれに Do 出⼒が瞬間的に全て Lo になってしまう時があります( Do データは変化していません。)これで問題はありませんか︖ | 外来ノイズなどの影響によりCLR端⼦の信号へノイズ等が乗り、Do出⼒がクリアされている可能性があります。 コンデンサなどによって負荷容量を⼤きくし、ノイズの影響を受けないようにしてください。 【参考資料】 テクニカルレポートNo.001 |
| MKY35とは、どのようなLSIですか︖ | HLSのサテライト素⼦として、⼊出⼒点数可変のI/O、カウンター、簡易PWM出⼒機能を内蔵した⼩型パッケージモデルです。 MKY34同様、センター素⼦からコントロールすることで、CPUを必要とせずに端末としての⼊出⼒動作を⾏います。 |
| MKY34 と MKY35 のカスケード接続について何かアドバイスしてください。 | カスケードに関するレポートをご覧ください。 【参考資料】テクニカルレポートNo.005 |
| MKY34 や MKY35 のカスケード接続は何段まで可能ですか︖ | カスケードに関するレポートをご覧ください。 【参考資料】テクニカルレポートNo.005 |
| MKY34 や MKY35 に接続するオシレータ(発振⼦)の選択⽅法を教えてください | 各ICに接続するオシレータは、共に発振可能周波数の範囲内であれば、セラミック発振⼦、⽔晶発振⼦のいずれでも問題ありません。 その場合に取り付けるコンデンサや抵抗といった負荷の選択は、発振⼦の種類やメーカや品種によって変わりますので、【参考資料】をご覧いただき、安定した発振動作が可能な周辺部品を選択してください(MKY34は4〜30MHz、MKY35は20〜50MHzの発振が可能です。それ以外の周波数による動作時には、XI端⼦に外部において発振済みのクロックを供給し、XO端⼦を開放にしてご利⽤ください)。 【参考資料】 テクニカルレポートNo.003, No.004 |
| MKY34、 MKY35 にオシレータ(発振器)を接続する際における Xi の⼊⼒レベルを教えてください。 | CMOSレベルを⼊⼒してください。VIH=3.5V(Min)、VIL=1.5V(Max)、lz=±10μA(Max)です。 ただし、TTL出⼒のオシレータであっても、負荷の軽い状態においてはCMOSレベル⼊⼒を満⾜する部品が多いので、その場合は使⽤可能です。 Xiに発振器を接続する場合は、Xoを解放してください。 |